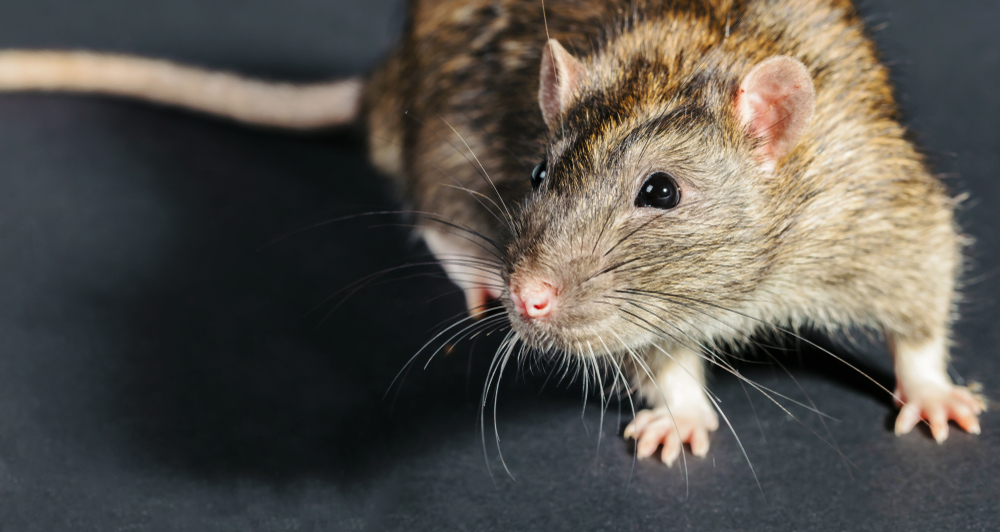ネズミが媒介する病気とは
ネズミはさまざまな病気を媒介することがあります。下記で、代表的なものを6つピックアップして紹介します。
レプトスピラ症
レプトスピラ症は、レプトスピラという細菌が原因で発症する病気です。主に動物の排泄物に汚染された土壌や水と接触することで感染が広がります。
例えば、カヤックや水泳などのレクリエーションで、体に傷がある部分や目、口などの粘膜から細菌が侵入することで感染します。
レプトスピラ症の潜伏期間は、2日から3週間ほどです。潜伏期間を経て、頭痛や発熱、筋肉痛、悪寒、吐き気、下痢、腹痛などの初期症状が現れます。重症化すると、体が黄色くなる黄疸の症状が現れ、肝臓や腎臓、さらには心臓や呼吸器系など、さまざまな臓器の機能障害を引き起こすことがあります。
現在、レプトスピラ症に対するワクチンは存在しないため、水に関わるレクリエーション時には、ケガを避けるために防護装備を着用するか、傷がある場合には水に入らないようにすることが重要です。
サルモネラ症
サルモネラ症は、細菌のサルモネラによって引き起こされる疾患で、急性の発熱、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐などの症状が現れます。感染は、細菌を含む食べ物を摂取することや、家畜・ペット・野生動物との接触を通じて広がります。
サルモネラ症は特別な治療を必要とせずに回復するケースが多いものの、幼児や高齢者、免疫力が低下している方が感染すると重度の脱水症状になり、生命の危険がともなうこともあるため、注意が必要です。
鼠咬症(そこうしょう)
鼠咬症(そこうしょう)は、ラットなどのげっ歯類に噛まれることによって引き起こされる動物由来の感染症です。げっ歯類の口腔内には、「モニリホルムレンサ桿菌」「鼠咬症スピリルム」という2種類の病原体が常在しており、噛まれると感染します。
モニリホルムレンサ桿菌感染症は、発熱や筋肉痛、回帰性の発熱、そして咬傷周辺に発疹が現れることが特徴です。
一方、鼠咬症スピリルム感染症は、リンパ節の腫れをともない、回帰性の発熱が続きます。どちらも放置すると命にかかわるリスクがあるため、早期の対応が重要です。
アナフィラキシーショック
アナフィラキシーショックは、極端に強いアレルギー反応によって全身に影響を及ぼす深刻な状態です。ネズミに噛まれたり、ネズミの排泄物に触れたりすることで発症する場合があります。これは、ネズミの唾液や排泄物に含まれるアレルゲンや病原体が原因となることがあり、アレルギー体質の方にとって危険です。
主な症状には、皮膚の発赤やかゆみ、蕁麻疹、息切れ、喉の腫れ、血圧の急激な低下などがあり、重症の場合は呼吸困難や意識障害を引き起こし、命に関わることもあります。発症した際には直ちに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが必要です。
E型肝炎
E型肝炎は、E型肝炎ウイルス(HEV)による感染症で、主に汚染された水や食べ物を介して感染します。感染すると、2~10週間の潜伏期間を経て、急な発熱や全身のだるさ、食欲不振、吐き気、嘔吐が現れ、数日後には黄疸(皮膚や白目が黄色くなる症状)が出ることがあります。
通常は1~6週間で自然に回復しますが、重症化すると回復に数か月かかるケースも少なくありません。特に妊婦は重症化しやすく、流産や早産のリスクが高まるため注意が必要です。
ハンタウイルス感染症
ハンタウイルス感染症は、ネズミなどのげっ歯類が持つハンタウイルスによる感染症です。ウイルスを持つげっ歯類にかまれたり、糞尿に触れたり、排泄物を含むほこりを吸い込んだりすることで感染します。ハンタウイルス感染症には、「腎症候性出血熱」「ハンタウイルス肺症候群」という2つの疾患があります。
腎症候性出血熱は10~20日の潜伏期間を経て、突然の発熱や頭痛、悪寒、めまい、腹痛、嘔吐などの症状が現れるのが特徴です。症状が軽い場合は自然に回復しますが、重症型では腎機能障害やショックをともない、死亡率が3~15%に及ぶことがあります。
ハンタウイルス肺症候群は、主にアメリカ大陸で発生している重症の呼吸器疾患です。突然の発熱や悪寒に続いて急速に呼吸困難が進行し、約40%が死に至ります。
ネズミが関与する病気
ネズミが直接媒介する病気ではありませんが、ネズミに寄生しているノミやダニによって発症する病気や疾患もあります。下記で2つ紹介します。
ツツガムシ病
ツツガムシ病は、「つつが虫病リケッチア」を保有するツツガムシに刺されることで発症する感染症です。潜伏期間は5~14日で、突然の発熱(38~40℃)、全身のだるさ、頭痛、悪寒、関節痛などの症状が現れます。
発熱後3~5日で赤い発疹が全身に広がり、刺し口の周囲のリンパ節が腫れることが特徴です。重症化すると肺炎や脳炎を引き起こすこともありますが、テトラサイクリン系の抗菌薬による治療で回復します。
日本では北海道を除く全国で発生し、特に春から初夏、晩秋にかけて多くみられます。感染を防ぐためには、野ネズミが生息する雑木林や畑などに入る際、長袖・長ズボンを着用し、ダニ忌避剤を使用することが有効です。
イエダニによる刺咬症(しこうしょう)
イエダニは、体長0.5~1.0mmの小さなダニで、ドブネズミやクマネズミに寄生し吸血します。ネズミの巣で大量発生し、ネズミがいなくなると吸血源を求めて人を刺し、激しいかゆみや発赤・発疹を引き起こします。
刺されやすい部位はおなかや太もも、腕の内側などの柔らかい部分です。イエダニの被害を防ぐには、まずネズミを駆除し、巣を撤去する必要があります。
ネズミから病気をもらわないためには?
ネズミから病気をもらわないためには、ネズミやその糞尿に直接触れないことが重要です。自力でネズミを駆除する際は、直接素手で触らず、使い捨ての手袋を着用し、捕獲後は適切に処理しましょう。
ネズミのフンにも病原菌が含まれる可能性があるため、片付ける際は手袋をし、終わった後はしっかり手を洗います。また、乾燥した糞尿がホコリとなり、吸い込むことで感染することもあるため、掃除の際はマスクやゴーグルを着用し、ホコリを巻き上げないように湿らせたペーパータオルで拭き取りましょう。
ネズミや糞尿を処理した後は、その場をアルコールで念入りに除菌・消毒してください。
ネズミの駆除方法
ネズミの痕跡「ラットサイン(糞尿やかじり跡、黒っぽい汚れ)」を見つけた場合は、病気に感染しないために早めの駆除が必要です。
下記では、自力でできる駆除方法を紹介します。なお、自力での駆除は衛生面のリスクがともなうため、可能であれば専門業者への依頼を検討してみてください。
罠を仕掛ける
ネズミを駆除するために、毒餌や粘着シートなどの罠を仕掛ける方法が有効です。罠は、ネズミの通り道や巣の近くに仕掛けましょう。また、罠を警戒されないよう、設置場所やエサの種類を変える工夫も必要です。
捕獲したネズミや死骸を処理する際は、直接触れずに手袋を着用し、密封して処分しましょう。駆除後は、ネズミの糞尿による汚染を防ぐために、しっかりと清掃・消毒をして再侵入を防ぐ対策もしましょう。
忌避剤で追い払う
死骸を「見たくない」「触れたくない」といった場合、ネズミを追い払う方法として忌避剤を使用するのが有効です。忌避剤にはいくつか種類があり、燻煙(くんえん)タイプは広い範囲で煙を拡散し、ネズミを遠ざけます。
スプレータイプは、ネズミ本体や通り道に吹きかけて追い払います。超音波タイプは、人間には聞こえない高周波音を発生させ、ネズミを不快にさせて追い払う仕組みです。それぞれ使用方法や効果が異なるため、状況に応じたものを選んでみてください。
ネズミを追い出す方法については、下記の記事でも詳しく解説しています。
「家からネズミを追い出す方法とは?正しい駆除・予防策」
ネズミの侵入を防ぐ
ネズミを駆除したり追い払ったりした後は、侵入経路を塞いで再び侵入するのを防ぎましょう。主な侵入経路としては、壁のひび割れや窓の隙間、ドアの下部、配管の周り、換気口、屋根裏の隙間などがあげられます。ネズミは1センチほどのわずかな隙間でも侵入できるため、家の周りや建物内の隙間をくまなく探して塞ぎましょう。
ネズミが棲みにくい環境にする
ネズミの侵入・繁殖を防ぐためには、餌を断ち、棲みにくい環境をつくることが大切です。食べ物の残りやゴミを放置せず、食事後にはしっかり片付けましょう。特に食料品は密閉容器で保管し、ゴミはしっかりと蓋をして捨てることが重要です。また、ネズミが隠れやすい場所を減らすために、家の中をこまめに掃除しましょう。
ネズミの駆除は実績豊富な「防除研究所」にお任せください
自力でのネズミ駆除は病気に感染するリスクがともなうため、専門業者に任せるのが賢明です。衛生管理のプロ集団「防除研究所」は、ネズミ駆除の実績が豊富にあり、専門的な知識やノウハウを有しています。
また、各種認証や規格も取得しており、駆除後は効果測定の結果を報告しますので、安心してお任せいただけます。エリアによっては即日対応いたしますので、ネズミの気配を感じたらすぐにご相談ください。
まとめ
ネズミが媒介する病気には、レプトスピラ症やサルモネラ症、ハンタウイルス感染症などがあげられます。また、ネズミに寄生しているノミやダニによって発症する病気や疾患もあります。
ネズミから病気をもらわないためには、死骸や糞尿に直接触れないことが大切です。衛生面のリスクを避けるためにも、ネズミ駆除は業者に依頼しましょう。